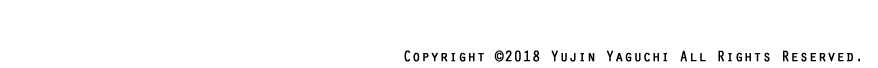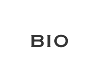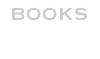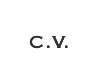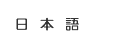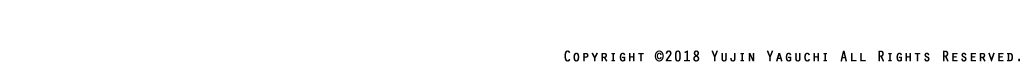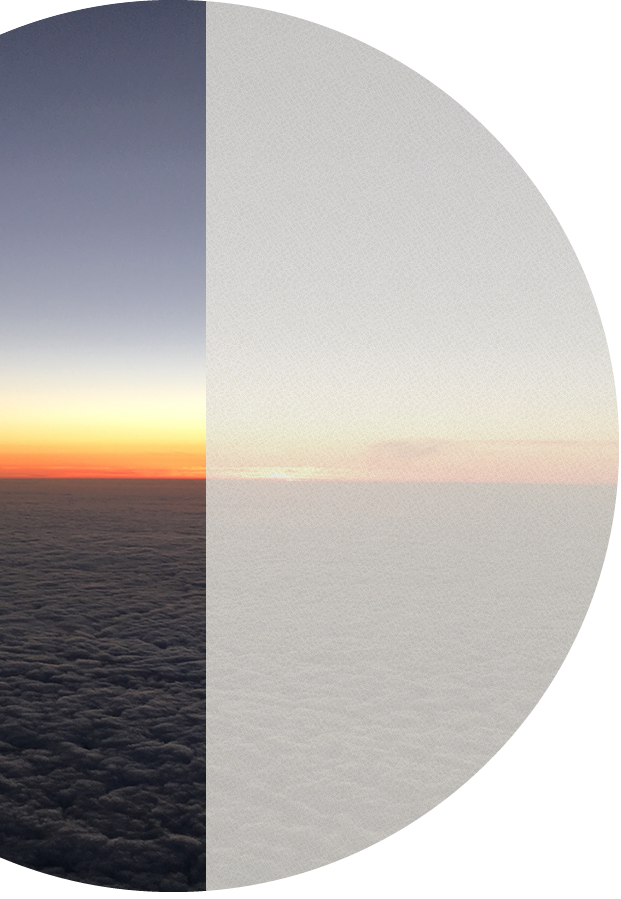
『なぜ東大は男だらけなのか 』集英社新書(2024年)

教授の9割、学生の8割が男性で占められる東京大学の歪んだ男女比は世界のトップ大学と比べて極めて異様である。このことが持つ意味を歴史と国際比較の視点から考察する。1945年以上前の東大と、戦後の東大を俯瞰する一方、プリンストン大学と東大の共学化の過程を比べることで、東大の構造が徹底的に日本男性の視点をもとに築かれていることを指摘している。これを解決することが、東大のみならず日本の社会をグローバル化するための喫緊の課題である。

『AIから読み解く社会 権力化する最新技術』板津木綿子・久野愛編 東京大学出版会(2023年)
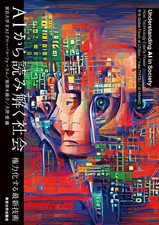
東京大学B'AI Global Forumを中心とするメンバーによる、AIと社会の関係について考える本。矢口の論考(歴史博物館におけるAIと歴史証言)はシドニーのユダヤ博物館で実験的に利用されているAIを使ってホロコーストの歴史証言者のホログラムに過去を語らせる試みについて考察したものである。

『岩波講座 世界歴史19 太平洋海域世界』中野聡 安村直己編 岩波書店(2023年)

矢口の論文「ハワイの内側から見るハワイ史」は太平洋の地域を外からではなく、先住民族であるハワイアンの視点から語ろうとする近年の学術的流れを紹介している。

Unpredictable Agents: The Making of Japan’s Americanists during the Cold War and Beyond , Mari Yoshihara, ed., (University of Hawai‘i Press, 2021)
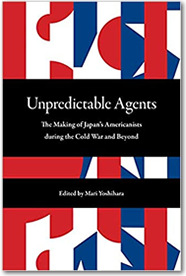
「日本のアメリカ研究者がアメリカとの出会いを個人的な体験から描き出すことで、冷戦期以降のアメリカを考える書。多様な背景を持つ研究者がそれぞれの「アメリカ」 を語ることで、「日米関係」を多面的に捉える試みである。“Learning ‘American’ from the Mennonites”という矢口のエッセイは幼少期からキリスト教を通して出会ったアメリカとそこから得た文化理解をまとめている」

『現代アメリカ講義』東京大学出版会(2020年)

2018年に東京大学で行われた「グレーター東大塾」の講演シリーズをまとめた、今日のアメリカ社会を知るための入門書。反知性主義、人種、ジェンダー、スポーツ、メディアなどの観点からトランプ大統領を生んだアメリカを多角的な視点から分析する。政治学、宗教学、歴史学、社会学など、一流の講師陣による講義がわかりやすくまとめられている。

Beyond Pearl Harbor: A Pacific History, Beth Bailey and David Farber, eds., (Lawrence: University Press of Kansas, 2019)
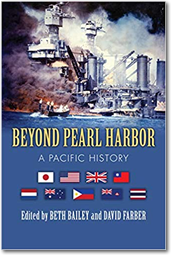
真珠湾攻撃75周年の2016年にカンザス州立大学で開催されたワークショップをもとにした書。真珠湾攻撃をグローバルヒストリーのなかで捉え直そうとする試みである。日米史や太平洋史に加え、中国、オーストラリア、フィリピンなどの視点から論考が集められている。矢口のエッセイは日本のメディアが真珠湾に言及した回数を調査し、日本における真珠湾攻撃の記憶の変遷を分析している。

Lon Kurashige and Madeline Hsu, eds., Pacific America: Histories of Transpacific Crossings, Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2017)

学術誌Pacific Historical Reviewに2014年に掲載された特集Conversations on Transpacific Historyを改編して刊行した書。編者のKurashigeとHsuに加え、Eiichiro Azuma, Brian Masaru Hayashi, Greg Dvorakらによる考察がおさめられている。矢口のエッセイは1956年に写真家名取洋太郎監修のもとに発刊された日系アメリカ人を特集した写真誌『日系アメリカ人〜ハワイの』(岩波書店)に現れる日系アメリカ人像を分析したものである。

キース・L・カマチョ著 西村明・町泰期訳『戦渦を記念する グアム・サイパンの歴史と記憶』 岩波書店 (2016年)

太平洋史の第一人者によるキース・カマチョによる北マリアナの歴史。グアムやサイパンなど、日本でもよく知られている島々とアメリカと日本の関係をアジア・太平洋戦争とその記憶の視点から論じた力作である。原著は2011年にCultures of Commemoration: The Politics of War, Memory and History in the Mariana Islandsとして刊行され、大平正芳賞を受賞した。矢口は翻訳版への後書きを執筆している。

『奇妙なアメリカ-神と正義のミュージアム』 新潮選書 (2014年)

ミュージアム(博物館・美術館・動物園など)はその社会の価値観を反映すると同時に、創り上げるものでもある。本書はアメリカにあるいくつかのミュージアムに取り上げをあて、現代のアメリカ社会を考える。たとえばアメリカでは人口の4割が進化論に否定的であると言われるが、その理由と背景を理解するためにカリフォルニアにある「創造博物館」を訪ねる。また南部アーカンソー州にある美術館「クリスタル・ブリッジズ」に焦点をあて、都市と地方の格差、美術コレクションと人種やクラスの関係などを考察する。

『憧れのハワイ―日本人のハワイ観』 中央公論新社 (2011年)
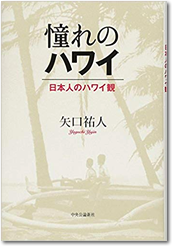
ハワイと日本は19世紀以降、深いつながりを持ってきた。戦前は多くの移民が日本から渡り、1941年には日本軍がハワイを攻撃することでアメリカとの戦争が始まった。戦後直後、戦災で荒廃した日々のなか、人びとは岡晴夫の「憧れのハワイ航路」を口ずさんだ。そして20世紀後半には日本からの観光客が激増し、ハワイは誰でも行ける観光地にもなった。本書は日本におけるハワイ観を概観し、ハワイが日本社会によってどのような意味を持ってきたかを分析する。優れた東西学術史の作品に与えられるヨゼフ・ロゲンドルフ賞(第27回)を受賞した。

『ハワイ王国物語―カメハメハからクヒオまで』 イカロス出版 (2011年).
 フラを学ぶ人のために、ハワイの王とその家族の視点からハワイの歴史を紹介している。フラの曲には王をはじめとするハワイの指導者を取り上げたものが数多くある。直接言及がなくても、花や動物などが王などを意味していることも少なくない。フラを演じる際には、これらの人物がハワイ社会にとってどのような意味を持つ存在だったのかを考える必要がある。本書ではハワイを統一しハワイ王国を打ち立てたカメハメハから、ハワイがアメリカに併合された後に活躍したクヒオまで、15人の重要なハワイアンを紹介する。
フラを学ぶ人のために、ハワイの王とその家族の視点からハワイの歴史を紹介している。フラの曲には王をはじめとするハワイの指導者を取り上げたものが数多くある。直接言及がなくても、花や動物などが王などを意味していることも少なくない。フラを演じる際には、これらの人物がハワイ社会にとってどのような意味を持つ存在だったのかを考える必要がある。本書ではハワイを統一しハワイ王国を打ち立てたカメハメハから、ハワイがアメリカに併合された後に活躍したクヒオまで、15人の重要なハワイアンを紹介する。

『真珠湾を語る−歴史、記憶、教育』矢口祐人・森茂岳雄・中山京子編 東京大学出版会 (2011年)
 アメリカでは「リメンバー・パール・ハーバー」(真珠湾を忘れるな)という表現がいまでも聞かれる。その際、何が記憶されるのだろう。そして何が忘れられるのだろう。また、そのような記憶の形成に学校教育はいかなる役割を果たしているのだろうか。本書は毎年夏に編者らがハワイで行ってきた日米の中高の教育者のための真珠湾ワークショップをもとに編纂したものである。テッサ・モーリス・スズキ、米山リサなどの著名な研究者による歴史の記憶を巡る理論的考察に加えて、中高の教育者による日米間の歴史教育に関する具体的な提案もおさめられている。
アメリカでは「リメンバー・パール・ハーバー」(真珠湾を忘れるな)という表現がいまでも聞かれる。その際、何が記憶されるのだろう。そして何が忘れられるのだろう。また、そのような記憶の形成に学校教育はいかなる役割を果たしているのだろうか。本書は毎年夏に編者らがハワイで行ってきた日米の中高の教育者のための真珠湾ワークショップをもとに編纂したものである。テッサ・モーリス・スズキ、米山リサなどの著名な研究者による歴史の記憶を巡る理論的考察に加えて、中高の教育者による日米間の歴史教育に関する具体的な提案もおさめられている。

Jenichiro Oyabe, A Japanese Robinson Crusoe, Greg Robinson and Yujin Yaguchi, eds., (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2009)
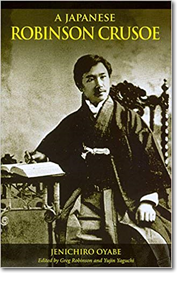 小谷部全一郎は19世紀末にアメリカに渡り、バージニア州のハンプトン実業学校とワシントンDCのハワード大学で学んだ。ハンプトンは解放奴隷とインディアンを対象に実業教育を提供する学校で、ハワードは同じく解放奴隷の黒人に教育を授けることを目的に設立された学校であった。なぜそのようなところに日本人の小谷部が通うことになったのだろうか。彼によるとそれは日本に戻って北海道に住むアイヌを「救う」ためであった。それはどのような意味を持つ行為だったのだろう。そして彼はほんとうにその目的を果たすことができたのだろうか。本書は小谷部がアメリカで刊行した自伝の再刊である。歴史家グレッグ・ロビンソンと矢口による長文の解説が付され、歴史資料をもとに小谷部の主張の分析がなされている。
小谷部全一郎は19世紀末にアメリカに渡り、バージニア州のハンプトン実業学校とワシントンDCのハワード大学で学んだ。ハンプトンは解放奴隷とインディアンを対象に実業教育を提供する学校で、ハワードは同じく解放奴隷の黒人に教育を授けることを目的に設立された学校であった。なぜそのようなところに日本人の小谷部が通うことになったのだろうか。彼によるとそれは日本に戻って北海道に住むアイヌを「救う」ためであった。それはどのような意味を持つ行為だったのだろう。そして彼はほんとうにその目的を果たすことができたのだろうか。本書は小谷部がアメリカで刊行した自伝の再刊である。歴史家グレッグ・ロビンソンと矢口による長文の解説が付され、歴史資料をもとに小谷部の主張の分析がなされている。

『ハワイ・真珠湾の記憶』矢口祐人・森茂岳雄・中山京子編 明石書店 (2007年)
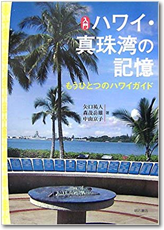
おもに中高生に向けたハワイ入門。ハワイはあまりに有名な観光地であるが、その歴史や社会の実情はあまり知られていない。本書は家族旅行や修学旅行などでハワイを訪れる中高生に向けて、ハワイをわかりやすく説明したものである。とりわけ日本の歴史教科書でも取り上げらえる真珠湾に紙幅を割き、アメリカとハワイでどのように「パールハーバー」が記憶されているかを紹介する。中高生のみならず、大人にもわかりやすいハワイ紹介として好評を博し、2018年に第3版が刊行された。

War Memories Across the Pacific: Japanese Visitors at the Arizona Memorial” Marc Gallicchio, ed., The Unpredictability of the Past (Durham: Duke University Press, 2007) 234-252.

アメリカ、日本、中国における第二次世界大戦の記憶に焦点をあてたたエッセイ集。矢口のエッセイはハワイの真珠湾を訪れる日本人観光客の戦争観を分析している。編者のマーク・ガレキオは優れたアメリカ史書に送られる「バンクロフト賞」を2018年にImplacable Foes: War in the Pacific, 1941-1945で受賞した。

『現代アメリカのキーワード』吉原真里と共編 中公新書 (2006年)

現代のアメリカ社会を理解するため、81のキーワードを取り上げた。最高裁判事の任命、健康保険を巡る論争、NAFTA、インターネットと政治運動、人種とスポーツ、肥満と社会など、今日のアメリカに重要なテーマを学際的に取り上げている。2008年に刊行した本書にはバラック・オバマ、ヒラリー・クリントン、オペラ・ウィンフリー、ヘイト・クライムなど、その後のアメリカ社会で大きな注目を集める事項が数多く含まれている。

『ハワイとフラの歴史物語』 イカロス出版 (2005年)
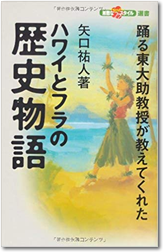
ハワイの歴史をフラの視点から紹介している。文字を持たなかったハワイ先住民にとって、フラは過去を称えることで、記憶する行為でもあった。フラはハワイの歴史そのものとも言えるのである。本書はおもにフラを学ぶ人のために、フラを通してハワイの過去の理解を深める試みである。

『ハワイの歴史と文化-悲劇と誇りのモザイク』 中公新書 (2002年)

誰もが知っているようで、意外と知らないハワイ。本書は移民、先住民、戦争、観光をテーマにハワイの歴史と今日の文化を論じる。一般読者向けの新書でありながらも、過去の新聞や雑誌資料、音楽や映画などからハワイ社会を丹念に分析することで、研究対象としてのハワイの深みをも紹介する。ハワイ研究の基本書として好評を博し、2016年に第5版が刊行された。